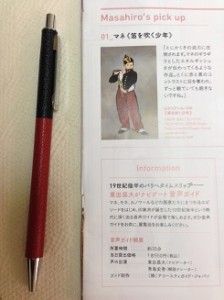本日は、盛りだくさんでございます。
まず、朝から伺いましたのが、出光美術館。
マリィ・プリマヴェラ先生からいただいたチケットを片手に、最終日に駆け込みました。
「宗像大社国宝」展。
最終日ですから、混んでいるわけですよ。で、宗像大社はうかがったことがないのですね。
なので、さほど強く響くこともなく……。歴史的に窓口だったのだなあというぼんやりとした印象で終わりました。
きっと参拝したことがあると、もっと興味深く鑑賞できたと予測します。鏡と指輪の文様は美しかったです。
あと、三十六歌仙図の斎宮女御の構図がかわいくて、かわいくて。というか、「大丈夫か? これ?」のポーズも
いっぱいありましたね。自由でよいです。戦利品はこちら。

時満ちて
道ひらく
素敵です。グッときます。
三菱一号館と迷ったのですが、期間限定のチケットを持っていることを思い出して、
新国立劇場へと向かいました。
チューリッヒ美術館展です。
これは、オススメです。なんだろう、オルセー美術館展より楽しかったかも!
オルセーもよかったですけれどね。というか、まだやっていてびっくりしました。オルセー美術館展は、20日までです。
チューリッヒ美術館展の何がよかったのかといえば、非常にコンパクトに美術史の流れがわかることでしょうか。
あと、日本初公開モノが多いのですね。だから、なんだか非常に新鮮なのです。
「おー、こう来たか」「で、そう来るか」みたいな。
ド頭はセガンティーニが2つ並ぶんですが、これがおもしろくて!
それぞれ、淫蕩さ、虚栄心がテーマなんですが、これだけ美しく描かれたら、
仕方ないよねって思っちゃいますね。何が仕方ないんだかわからないんですけれど。
淫蕩さも、虚栄心も、美しい。どんな事件があり、どんな女性に出会うと、ああいうインスピレーションにつながるのか、
そこに興味があります。
で、モネの大作です。
あっけにとられました。よく、日本に持ってきましたね。
ホドラーのドラマチックさ、ヴァロットンはいろいろ並べるより、《訪問》一枚で伝わるような気がしますし、
バルラハの《難民》は監視のお姉さんにマークされるくらいジロジロ、ぐるぐる見ちゃいました。
大丈夫、触りませんよ。舐めるように見ているだけです(よしなさいって)。
個人的な収穫は、シャガールかもしれません。
今まで、いまひとつ好きになれなかったのですが、「ああ、奥様は亡命中に亡くなったのか」と
やっと作品の背景に気づきました! これから見方が変わりそうです。
ごめん、ずっと誤解していましたよ、シャガールよ!
まあ、それほど作風が響かないから、当然、画家の半生にも興味が持てず……。
きょう、たまたまついていた説明で、「あれ?」と目からウロコが落ちたのでした。
なんというか、「お幸せでよろしゅうございますね(棒読み)」みたいな距離の取り方でした。
フェルナン・レジェの《機械的要素》も、説明文でぐっと楽しくなりました。
戦争を経験して、作風がガラッと変わる、あるいは、深みを増す画家さんが多い中、
機械美に魅せられるって、なんだかもう興味深いです。
絵だけを見たら、なにがなんだかですけれど、でも、その背景を想像すると
「そうか、そうか、そうなんだね」みたいなよくわからない相槌を打っておりました。
絵の前でうなづく女、客観的に見たら、相当不気味ですが。
ジャコメッティで、幸せなひと時は終わりました。
ちょっと迷ったけれど、もう一度モネの大作を眺めて、締めました。

数あるグッズの中で買ったのは、一筆箋。
次に用事がなければ、絶対クッキーを買いましたね。
だって、「モネ」とか、「ゴッホ」とかカタカナでクッキーに書いてあるんですよ。
ツボに入ったけれど、荷物になるので、諦めました。
買えばよかったかなー???

アークヒルズに移動しまして、お昼を食べました。
バビーズ ニューヨークのブレックファストなんちゃら。
食べきれませんっ。無理、無理、無理!
パンケーキが分厚いんですよ。
で、ちょっとだけ、メープルシロップのつもりがジャカジャカかけるハメに。
鬼のようにポテトもあるし、ソーセージもあるし、ハムもあるし、ベーコンもあるし。
完全に負けました。
で、やっとサントリーホールのブルーローズへ。
宮田まゆみ先生の「調子・入調」です。
いやー、すごいですよ。
貴重な体験をさせていただきました。
調子のイメージ、変わりました。
私が雨のイメージだった(これは笙仲間さんたちにも「なぜに雨?」と聞かれてしまいました)
平調の調子(ちなみに、ひょうじょうのちょうしと読みます)は、
演奏前に宮田先生が「月の光が」とおっしゃったことから、イメージが一新され、
聞いているうちに、頭の中で月の宮殿が建ちました。
機織りのイメージも喚起されます。
平調の入調は、初めて聞いたのですが、月明かりの下の遊びのようです。
余談ですが、私が生まれて初めて見た商業演劇は浅丘ルリ子さんの『十三夜』、
冒頭、「影、影」と子供が影踏みをして遊ぶのです。
月遊びの連想で、ぼんやりと思い出しました。
春のしらべである双調は、春は春でも、春を告げる鳥のよう。
自然に湧き出る春の息吹ではなく、揺り動かす春の精のように感じました。
双調の入調は、閉じられていた扉が開く感じでしょうか。
黄鐘調の調子は、忘れられていた古代都市の風景が浮かびます。
黄鐘調の入調は、修復の魔法みたい。
あはは、勝手なことを並べております。
私、音楽を聞くのがニガテなんですよ。
いつも勝手に物語に置き換えて聞いています。
ああ、もう一回、最初から聞きたいです。楽しかったです。
あ、そうそう、意外に、一夜漬けが効きましてね、
「あ、今、五句だ」とか、「そうそう、五句からくりかえしで、十五、十六で終わり」とか、
意外に入っていました。ブラボー、一夜漬け!
12月に残り三つの調子が聞けます。とても楽しみにしております。

最後に、台風が近づく中、オーバカナルでお茶をしました。
おなかいっぱいのくせに、目が欲しくて頼みました。
いちじくのタルトで、幸せな一日の締めくくりです。
え? 芸術の秋じゃない、食欲の秋だって? 放っておいて!