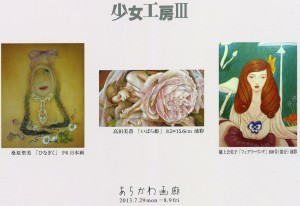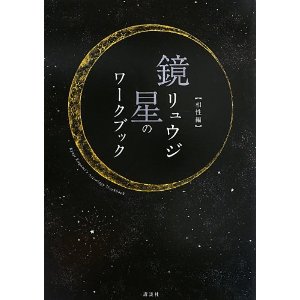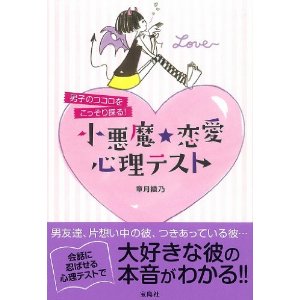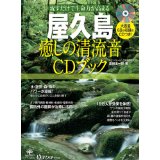きょうは、先生の演奏会にうかがいました。
先生は、怜楽舎という雅楽団体に所属されているのですが、笙の演奏者さんで
ユニットを結成、それが、shogirlsというそうです。
三浦礼美、田島和枝、中村華子さんの3人です。
こちら、一回目はうかがえなくて、今回、初めて拝聴しに行きました。
場所は、初台オペラシティ・近江楽堂。
初めて入りましたが、美しい空間ですね。
3管の笙に、正倉院復元楽器である竿の演奏でした。
竿、読めます? 「う」と読むのです。
非常にタテに長い楽器で、今回は立ったまま演奏されていましたが、
重いんじゃないかしら?とぼんやり眺めておりました。
演奏者が違うと、笙の音は違うのです。
それが、非常によくわかりました。
笙仲間さんや三浦さんの衣装を作られた森千春さん、
カメラマンの泉谷典彦さんなど、顔見知りの方がたくさんいらして、
あちこちにあいさつしていたら、誰かに「顔が広いねえ」って言われました。
違いますよ!!! みんな、先生のご紹介なんですよぉ。
先生にご挨拶をして、なぜか会場の椅子も片付けて(おかしいなあ、お客さんのはずだったのに?)、
それから、東京オペラシティアートギャラリーに立ち寄りました。
開催されているのは、「アートがあればⅡ」。
9人のコレクターさんたちによる個人コレクションの展示です。
面白い企画ですよねー!
現代アートは、基本的にわからないことだらけなのですけれど。
なぜか、泉谷さんが「僕も見ようかな」ってことなって、ご一緒しました。
写真の展示も多く、プロのカメラマンの解説つきで、非常に贅沢な時間となりました。
ちょっと面白かったのは、「タイプCプリントって、何?」って泉谷さんがおっしゃることです。
いや、あなたにわからないこと、私にわかるわけないじゃないですかぁぁぁ!
調べました。
「タイプCプリントとは、コダックの発明した発色印画方式のプリントのことです。
つまりごく普通のネガからのカラープリントのこと。(以下略)」
インターネットって、便利ですねえ!!!
写真のことなど、てんでわからないので、
「そうかあ。カメラやっていれば、絶対知っている人なのになあ」と微妙にガッカリさせながら、
進みました。まあ、知らないものは仕方ないっすよね!(開き直り)。
写真だけじゃなくて、絵画からオブジェなど、いろいろなものがありまして。
ぶっとんでいたのは、大型のラジコンカーにファーを着せて、犬ぞりみたいにしていたやつでしょうか?
映像もついていて、本当に走るみたいです。乗りたーい!
渋谷センター街でつかまえたネズミを剥製にし、着色し、ピカチュウ仕立てにしているのもありました。
捕まえる様子の映像つき。「飛ぶ、飛ぶから」とギャルが叫んでいて、渋谷のネズミは飛ぶのかーって
思ったら、非常に、シュールな気分になりました。
アートって、すごいなあ!!!
そんな風に型破りなモノが多いため、福島の映像も作りものに思えて。
泉谷さんに「いや、これ、フクイチでしょ」って言われて、ハッとしまして。
もう何が虚構で、何が現実なのかわからなくなるのです。
まあ、私が鈍いだけかもしれません。
後半、昔の写真をコレクションされている方のコーナーがありました。ここは、非常にホッとしました。
ブラッサイ、アンリ・カルティエ=ブレッソン、ロベール・ドアノー、いやあ、色っぽくていいですね。
「有名な写真だよ」そうなんですかー(バカ丸出しだなあ、我ながら)。
マンレイの手法についても、教えていただいて。へええでしたよ。
収蔵展に行く前に、不思議な双眼鏡みたいなものとヘッドホンのコーナーがありまして。
そのときは、他のお客様がいらしたので、先に収蔵展を見て戻ったのですが。
帰りがけに見せていただいたら、たいそう素敵なものでした。
星空に、メッセージがうかぶのです。BGMつき。
メッセージは、星の王子様の中の言葉だそうですよ。キレイ!!!
いろいろ教えてくださった方、あの方、作家さんだったのかしら? 聞けばよかったです。
おかげで、後味よく帰れました。
この9人のコレクションの中で、ひとつだけもらえるとしたら、いや、もらえませんが(笑)、
小出ナオキ氏の「Devil on elephant」です。
デビルも、象もツボります。いいなあ、私も欲しいなあ。いや、買えまい。
しかし、かわいいんです。あ、星の王子様セットもいいかも。あーでも、デビルかなあ?
心底、どうでもいい迷いですね。
いろいろなものが詰め込まれていて、面白いですよー!
9月23日までやっているそうです。
そうそう、「響会Ⅱ」の前には、サントリー美術館にも寄ったのです。
谷文晁展、後期です。
「石山寺縁起絵巻」も、展示替えになっていて、紅蓮の炎が素晴らしくて。
炎の色に、黒が混じるのが、迫力の秘密でしょうか?
よーく見ると、生首をぶらさげている人もいたりして。
サントリー版をジロジロ見て、重要文化財版を見比べようとして、
見事、ガラスにごっつんしました!
そういう人、たまにいらっしゃいますが、まさか、自分がやるとは!!!
強化ガラスだとは思いますが、割れなくてよかった! 本当によかったです!!!
あーいうとき、痛いんですけれど、とりあえず、おかしくて仕方ないですね。
くくく、どこまでのめりこんで見ているのでしょう???
そして、根津美術館所蔵の「赤壁図屏風」が素晴らしいんですよ。好き、好き!
あ、奥様や文一が亡くなった年に注目してみるの、まんまと忘れました。
25日までにもう一回行けるかなあ??? 行けますように。
というわけで、きょうも詰め込みました。どうして詰め込んでしまうんでしょうねえ?
我ながら、よくわかりません。自分のことが一番わからないから、ま、いっか。